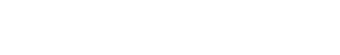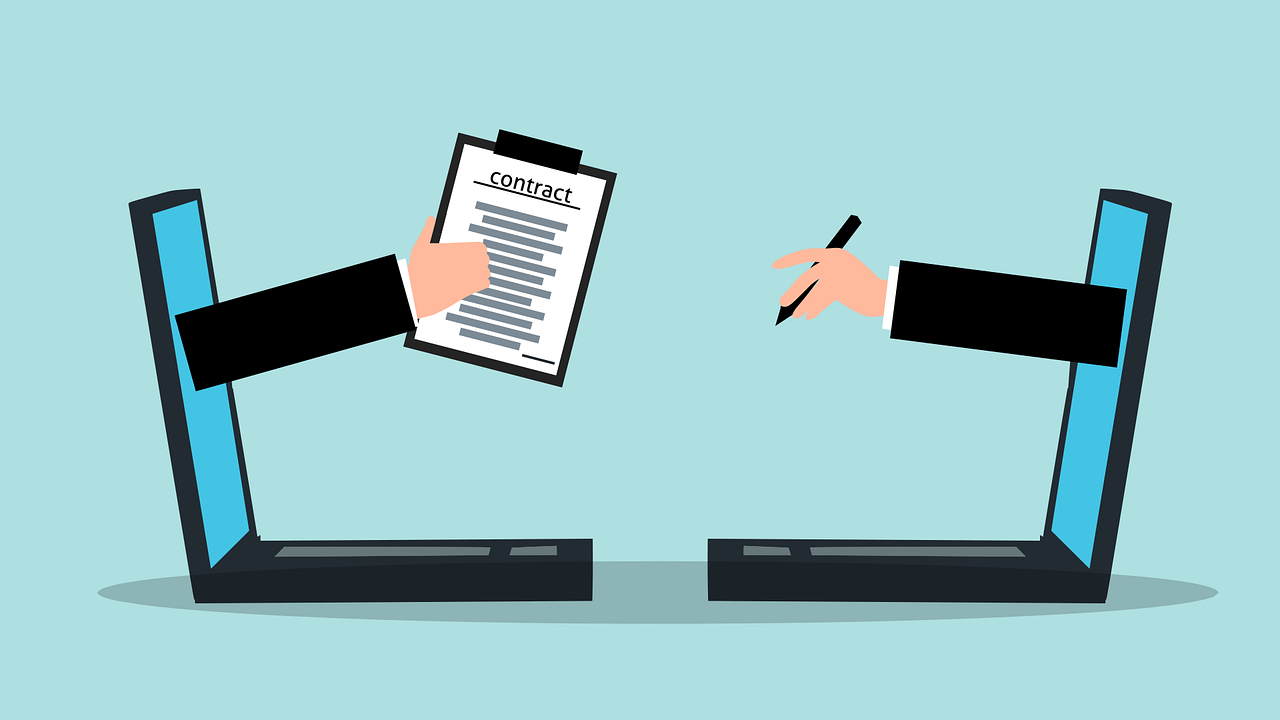こんにちは。スリープラスの徳永です。
SE・プログラマーがどういったシステムを製造しているのか、気になる方もいるかと思います。
私が業務で携わっているシステムは、購買管理システムといい、様々な購買業務をシステム化したものになります。
初めに購買管理システムと聞いた時は、どんなことをしているのかイメージがあまりつきませんでした。
購買管理システムについて説明する前に、システムの扱っている購買業務とはどういった仕事なのかを初めに説明します。
そのあとで、購買管理システムとは、いったいどういったものなのか簡単に説明していこうと思います。
購買業務とはどういった仕事か
購買業務とは、企業活動に必要なものを購入することです。
物を購入する際、買い手としては当然商品を安価で購入できる方がうれしいですが、安ければよいというわけでもありません。
いくら商品が安くても品質が悪かったり、納期通りに発注されなかったりした場合却って会社に損害を与えてしまいます。
つまり、買い手が適切だと判断する値段、品質を見極め、納期通りに購入できるようにすることが購買の主な仕事となってきます。
購買の主な仕事の流れ
- 見積依頼書の作成
- 見積書の取得
- 見積の評価など
- 注文書の作成
- 発注実施
- 注文請書の取得
- 納品
- 納品物の数量・品質を確認
- 支払い
見積処理
物を購入したいとの要望があれば、それに応じて適切な見積先を決める工程です。
要望には、5W1Hが指定された具体的な物から、漠然とした要望まで様々です。
これらに対して、見積依頼書を作成します。
見積依頼書とは、取引先に対して、「この商品をこれだけ買うといくらになりますか?」とたずねる代わりの文書となります。
この見積依頼書をもとに取引先を選びます。
取引先から見積書を受け取ると、見積書を比較し適切だと判断した取引先を決定します。
発注処理
発注処理は、見積内容を元に取引先へ注文を行い、商品が発注されるまでの工程となります。
取引先を選定した後、注文を行う際購入者は売買契約書や注文書といったものを作成します。
こちらは、見積書をもとにこれらの商品の発注お願いします。
といったような意味合いを持つ文書です。
注文書などは必ず必要になるわけではなく、口約束などでも可能ですが、言った、言わないなどのトラブルを避けたり、商品や数量などを間違ってしまうリスクも減るため、作成した方がよいとされています。
取引先は注文請書を作成し、発注を承ったことを約束します。
こうして発注が行われることになります。
受入処理
受入処理は商品の納入を行い、検品した後取引先へ支払いを行う工程となります。
発注の後は、購入者は納期通りに納入できるようにフォローを行います。
これも購買の仕事になってきます。
納入されたら商品を確認し品物を受け取ったという証明となる検収書というものを作成します。
取引先は検収書を取得し確認ができれば、支払いへと移ります。
以上が、購買業務の一連の流れとなります。
購買管理システムとは
上記の購買業務以外にも、実際にはもっと多くの購買業務があります。
それらをシステム化したものが購買管理システムです。
購買管理システムを使用することで生まれるメリットとしては、業務の効率化や情報をまとめて管理できる点があります。
例えば、この商品を購入したといった要望があった場合、商品名で検索を行うと過去にその商品の取引を行ったデータを取得でき、簡単に比較が可能です。
蓄積されたデータを瞬時に取得できるといったことは購買の仕事である、適切な値段、品質、納期を見極めるといった作業にとても役立ちます。
また、見積依頼書などの文書フォーマットを作成しておくことによって面倒な作業やミスを減らすことができます。
このように、手間のかかる作業をできるだけシステムにやってもらい業務を効率化することや、より正確な購買を行えるようにするのが購買管理システムとなります。
苦労したこと・大変だったこと
購買の流れを理解することが苦労したことです。
決裁であったり、見積書などの文書の出力であったりと、どういった意味があり、どのタイミングで行うのかしっかり理解していなかったため、複雑な手順のように感じていました。
また、流れを理解できていなかったために購買管理システムを操作する際に欲しいデータを取得できず、何をするにも時間がかかってしまいました。
しかし、テキストなどで購買の基礎知識を少しずつ身に着けていったことで、各機能で何を行っているかが分かるようになっていきました。
その結果、複雑な手順のように感じていた処理も購買の知識と照らし合わせて考えることでスムーズに理解でき、取得したいデータも時間をかけず出力できるようになりました。
最後に
購買に初めて触れると、見慣れない言葉や考えが沢山出てきます。
分からないことが多くあるとどうしても不安になってしまうかと思います。
しかし、少しずつでよいので理解していくことで次第に慣れていくと思うので、学習を続けていくことが大切だと思います。
この記事を読んで少しでも興味を持つきっかけや購買の理解に役立てたのなら幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。